 美容
美容 50代 自分に合ったメイクの色を選んでくれるBIJOUM
先日、わたしが通い始めた「美塾」の創始者である内田裕士氏が監修しているコスメブランド「BIJOUM(ビジューム)」で催されたZoomメイクレッスン会に参加しました。 「毎朝、自分の顔が好きになる」の著者とZoom越しに会えた! わたしが美塾...
 美容
美容  美容
美容 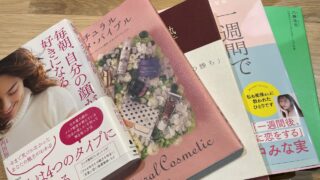 美容
美容  美容
美容  日記
日記  日記
日記